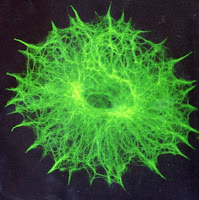バートン・フィンク

ブロードウェイでの成功を夢見ていた脚本家が、映画会社社長に見込まれて、ハリウッドに進出する。映画会社で出会う社長も、プロデューサーも、かつて尊敬していた脚本家も、人格崩壊寸前のストレス人間ばかり。宿泊した安ホテルには、とびぬけて「キレた」キャラクター、謎の保険勧誘員が泊まっていた。いつの間にか狂気の都ハリウッドに渦巻く、毒気あふれる乱気流に飲み込まれ、脚本家本人も、ついに抜き差しならない悲劇のまっただ中に放り出される。 コーエン兄弟作品に共通するテーマとは何か。「理不尽におそいかかる運命と闘うおろかなる人間」の姿を描くことではないだろうか。そしてその「おろかなる人間」を、映像を通して造形していく腕前が素晴らしく、「理不尽な運命が」哲学的なメッセージを含んだ、鮮やかな語り口の脚本に託されると、彼らの作品はひとつのマスターピースへと結晶する。スクリーンに不思議な後味を残して。 コーエン兄弟作品は、つねに神の視点のような「高み」から、クールに語られる。神の視点から見れば、一般庶民が生活の中で体験する、悪夢のような出来事も、まるでデパートのカタログの1ページのようなもの。複雑に絡み合った事件、わけのわからない取引、意味不明な人間関係。そうしたものも、神から見ればすべては「はじめから決まった運命」の展開に過ぎないのだろうから。しかも、コーエン兄弟の映画の視点は、同時に映画のキャラクターへの愛情あふれるまなざしでもある。まるで、神がわれわれの愚行を許してくれるように、カメラはどんな悲劇も喜劇も、ただただ冷静に見つめるだけだ。 つづきを読む>>>